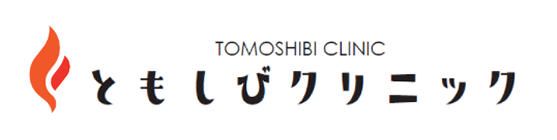「なんで毎日こんなに疲れるのかな」「わたしはこんなに疲れているのに、あの人の元気がうらやましい…」と悩んでいませんか?
忙しい現代では、しっかり寝ていても慢性的に疲れを感じている方が少なくありません。なかには、自分の疲れやすさは生まれつきなのかなと、毎日ため息をついているという方もいらっしゃるでしょう。
その疲れやすさは、生活習慣や環境のほか、生まれつきの体質ということも考えられます。
本記事では、疲れやすい体質の原因や特徴、疲れやすさを解消するための方法について解説しています。
毎日を元気に過ごしていくためにも、ぜひ参考にしてください。
疲れやすい体質の原因とは?生まれつきだけではない3つ理由
疲れやすい体質の原因には、生まれつきだけではない3つの理由があります。それぞれひとつずつ見ていきましょう。
1:生活習慣による疲れやすさ
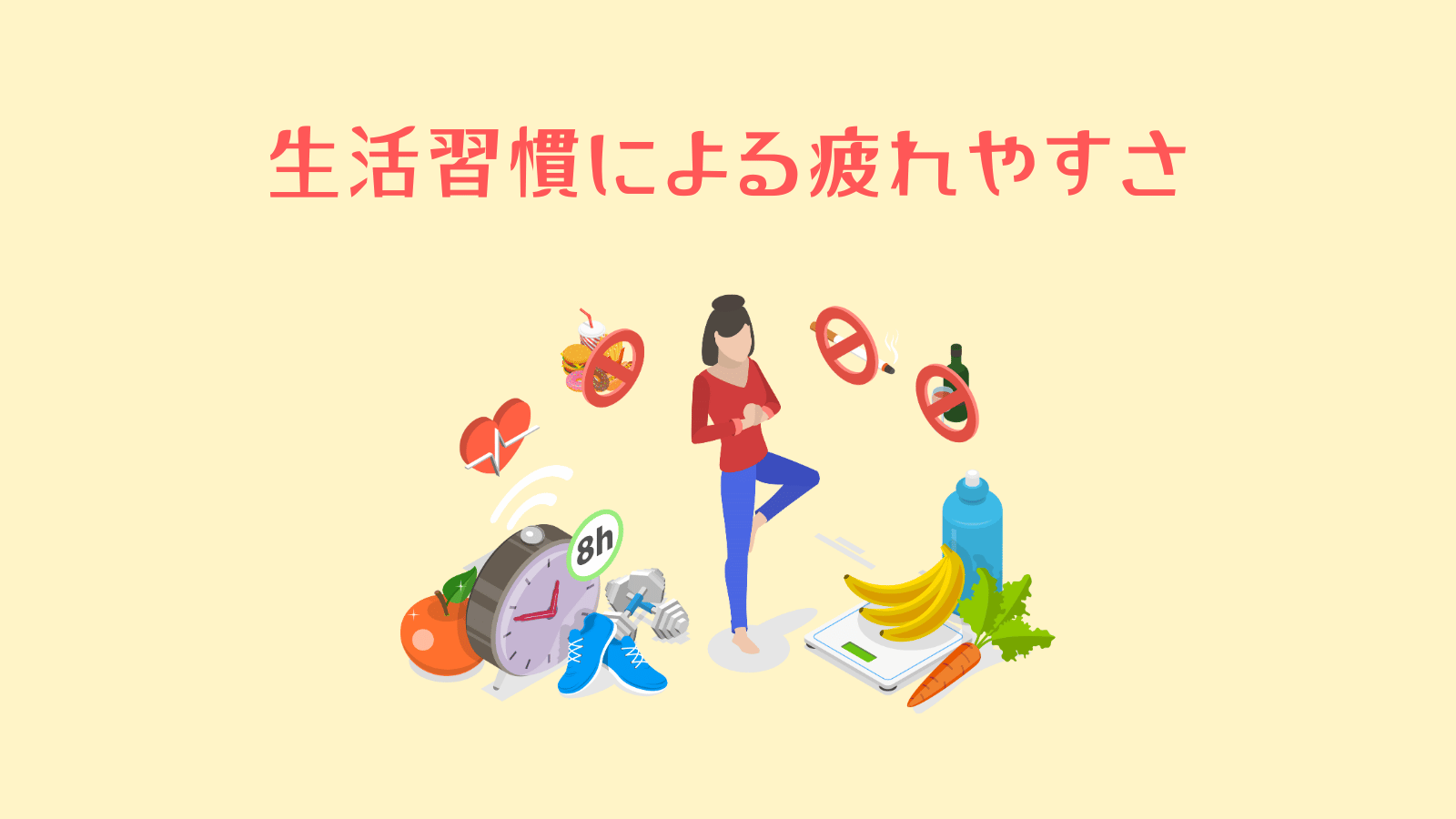
生活習慣の乱れは、体のリズムを大きく崩すため疲れやすさの原因となります。具体的には、偏った食事や睡眠不足、運動不足の3つが挙げられます。
まず、偏った食事や過度なカフェイン・アルコールの摂取は、体に必要な栄養素を不足させ、日中の活動に必要なエネルギーを作れなくします。
体の細胞を作るのに必要なタンパク質が不足すると、体力不足・筋力不足の低下を招いてしまうほか、エネルギー源となる糖質が不足すると、少しの運動でも疲労を感じやすくなるのです。
また、睡眠不足や就寝・起床時間の不規則さは、自律神経のバランスを乱し、体力の回復力を低下させてしまいます。
人の体には約24時間周期の体内時計(概日リズム)があります。睡眠不足や睡眠の乱れはこのリズムを狂わせ、食欲や体温調整、ホルモン分泌などの働きが不安定になり、結果的に常にだるさや疲労感を感じやすくなるのです。
さらに、運動不足は体内の血流を悪化させ、老廃物の排出も滞りやすくなるため、だるさを感じやすくなります。運動不足は筋肉の衰えにもつながりやすく、体中の筋肉が減ると基礎代謝が下がり、エネルギーを燃やす力も低下。少しの活動でも疲れやすくなり、動かないと体力が落ちるという悪循環に陥ります。
このように、生活習慣の乱れは心身両面に影響を及ぼし、慢性的な疲労体質をつくってしまうのです。
2:環境による疲れやすさ
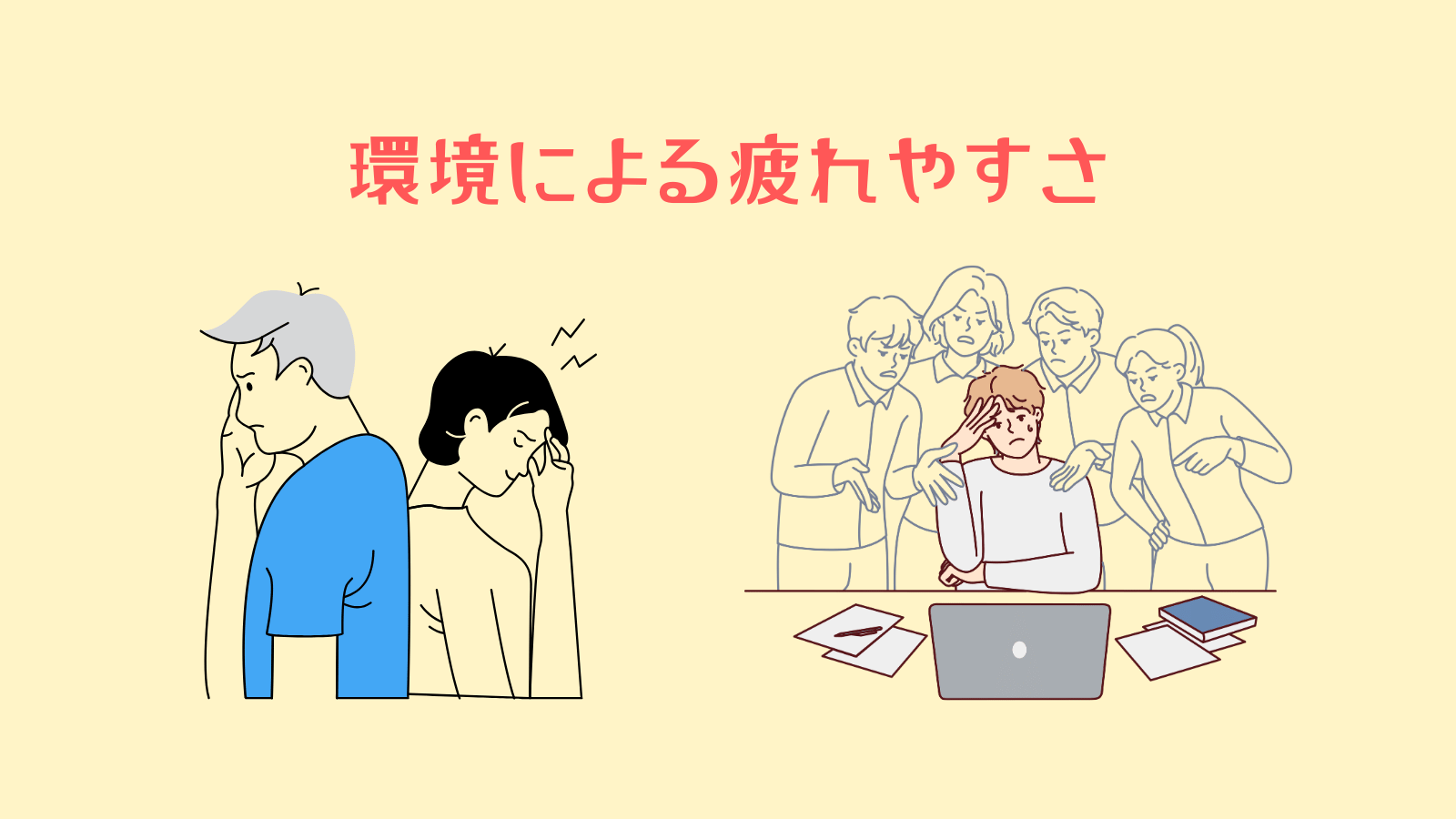
職場や家庭における人間関係といった外的要因など、心身に大きな負担を与えることも疲れやすさの原因のひとつです。例えば、人との摩擦や過度な気遣いは精神的ストレスを増大させ、エネルギーを消耗します。
また、周囲からの期待や過度なプレッシャーがあると常に緊張状態が続き、自律神経のバランスが乱れやすくなります。その結果、心身の回復力が低下し、慢性的な疲れを感じやすくなるのです。
3:HSP気質や虚弱体質による疲れやすさ
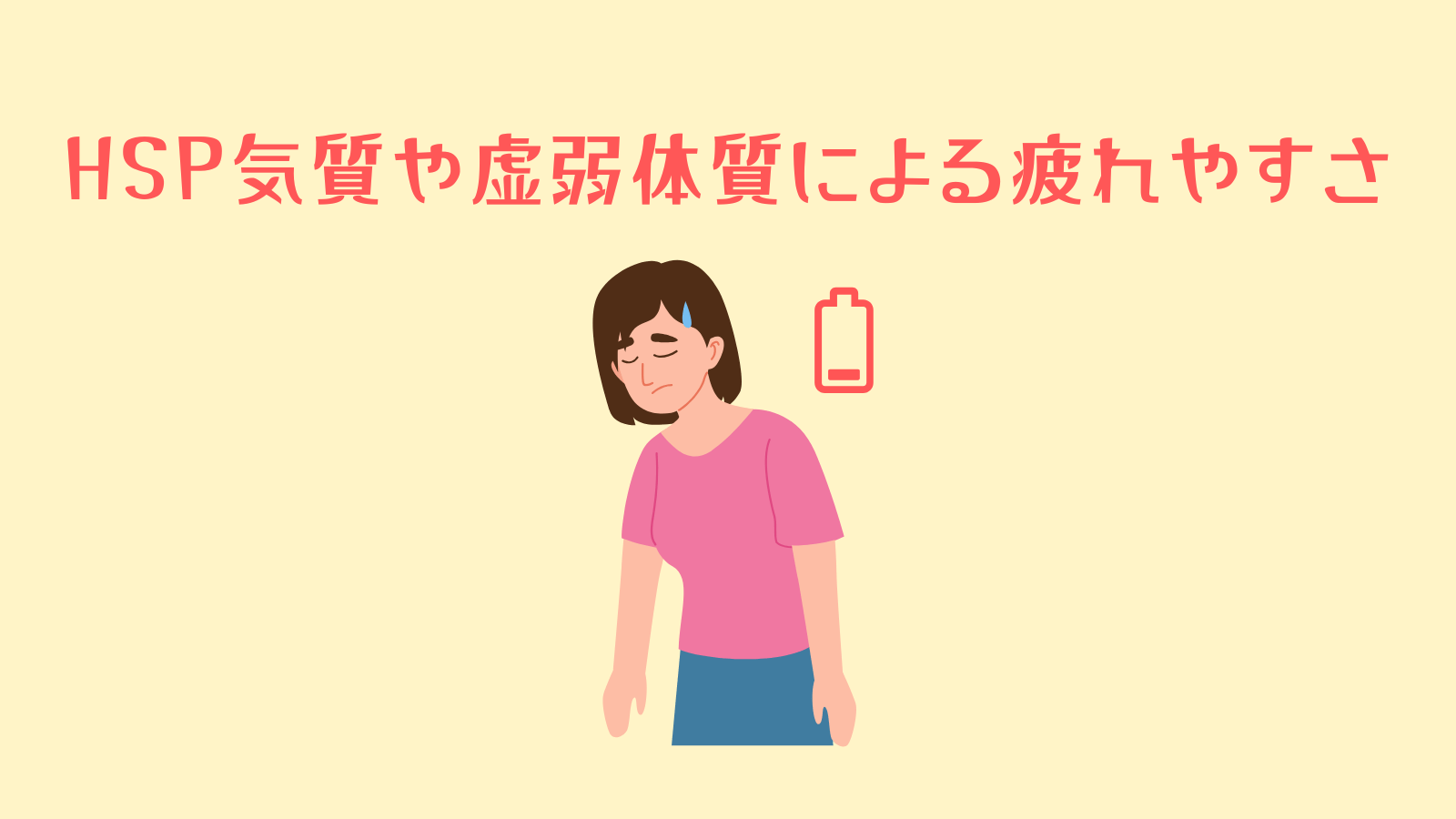
HSP(Highly Sensitive Person)は人よりも刺激に敏感で、音や光、人間関係の雰囲気などから強い影響を受けやすく、心身のエネルギーを消耗しやすい特徴があります。人との会話や人混みといった日常的な場面でもエネルギーを消耗しやすく、休息をとらないと心身がすぐに限界に達してしまいます。
虚弱体質の人は生まれつき体力や免疫力が弱く、ちょっとしたストレスや気温の変化でも疲労を感じやすい傾向があります。これらの特性が重なると、通常なら気にならない出来事でも大きな負担となり、慢性的な疲労感へとつながりやすいのです。
参考:虚弱者に多い自覚症状
疲れやすい体質な人の5つの特徴
1:完璧主義
2:周囲の目を気にしすぎる
3:共感する能力が強すぎる
4:自己否定が強い
5:常に何かを考えている
疲れやすいと感じる方にはある特徴があります。ここでは、疲れやすい体質な人の特徴をみていきましょう。
1:完璧主義
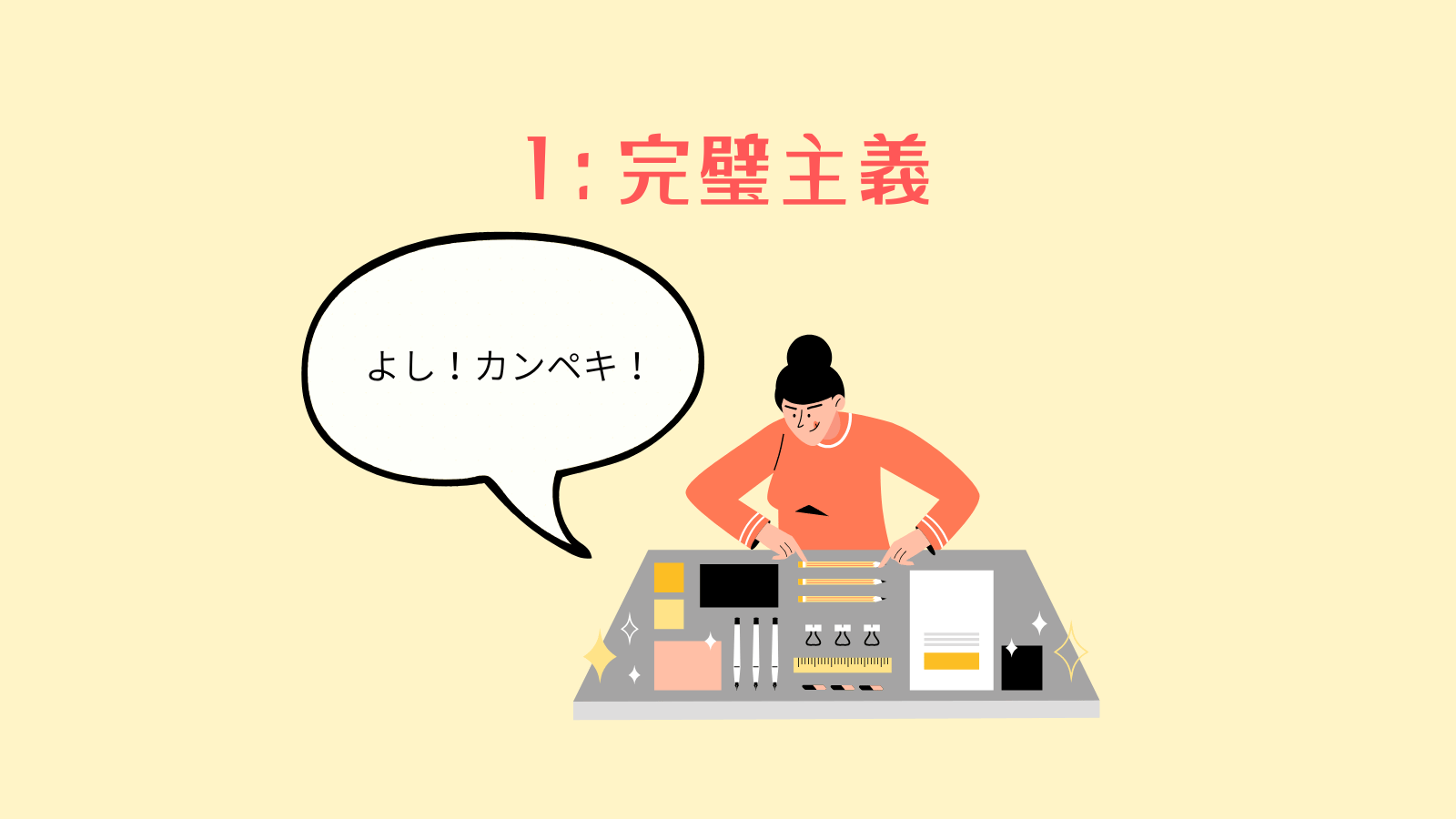
完璧主義の人は、常に「失敗してはいけない」「もっと今より良くしなければ」と自分に強いプレッシャーをかけ続けます。
その結果、心が常に緊張状態にあり、些細なミスでも大きなストレスを感じやすくなります。休むことにも罪悪感を覚え、心身を十分に回復させられないため、慢性的な疲れやすさにつながるのです。
2:周囲の目を気にしすぎる
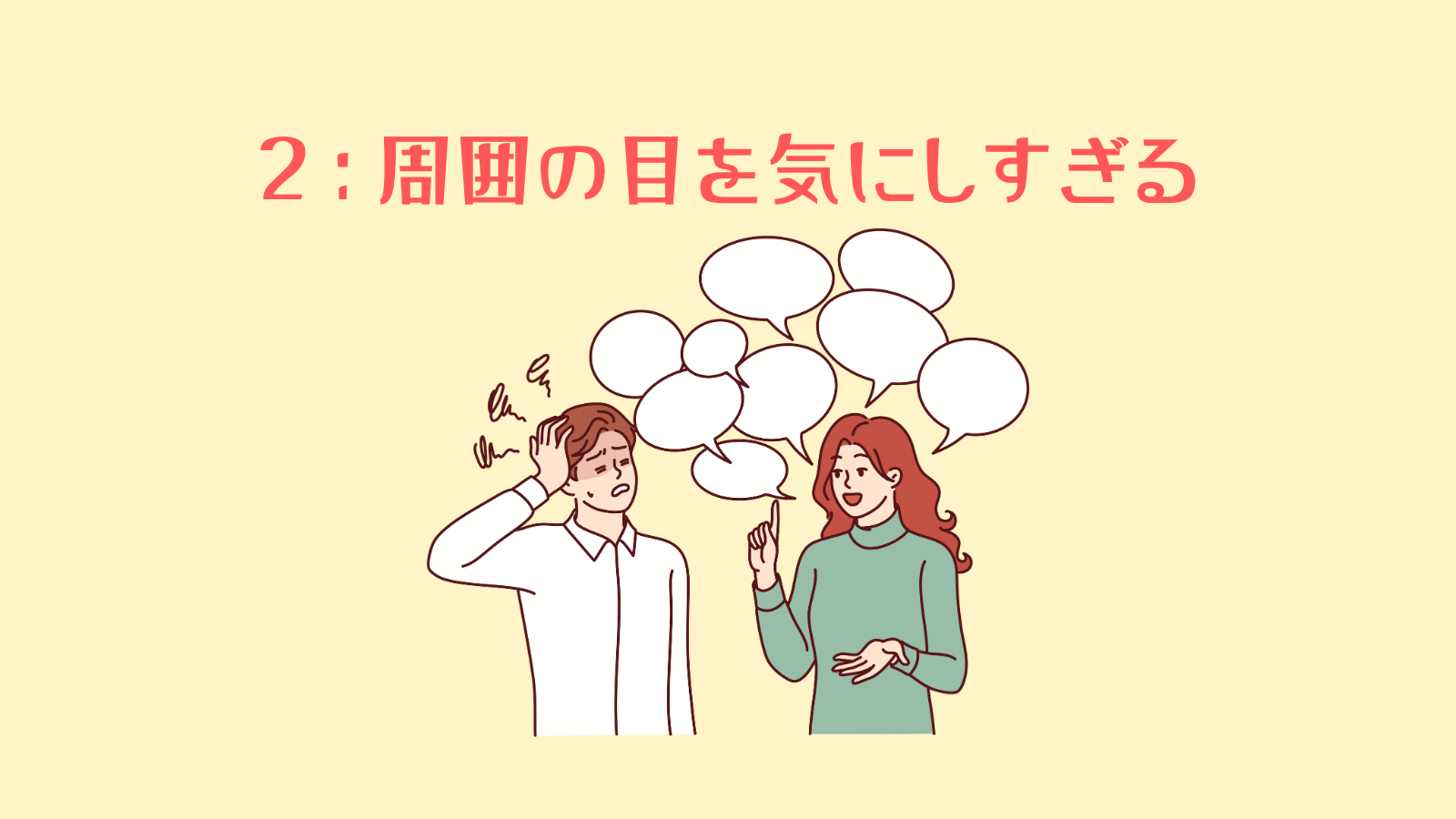
周囲の目を気にしすぎる人は、常に「どう思われているか」を意識し続けるため、無意識のうちに緊張やストレスを抱えています。
人前での言動や評価を気にして自分を抑え込むことが多く、心が休まる時間が少ないのが特徴です。その結果、精神的な疲労が蓄積し、体にもだるさや疲れやすさとして表れやすくなります。
3:共感する能力が強すぎる
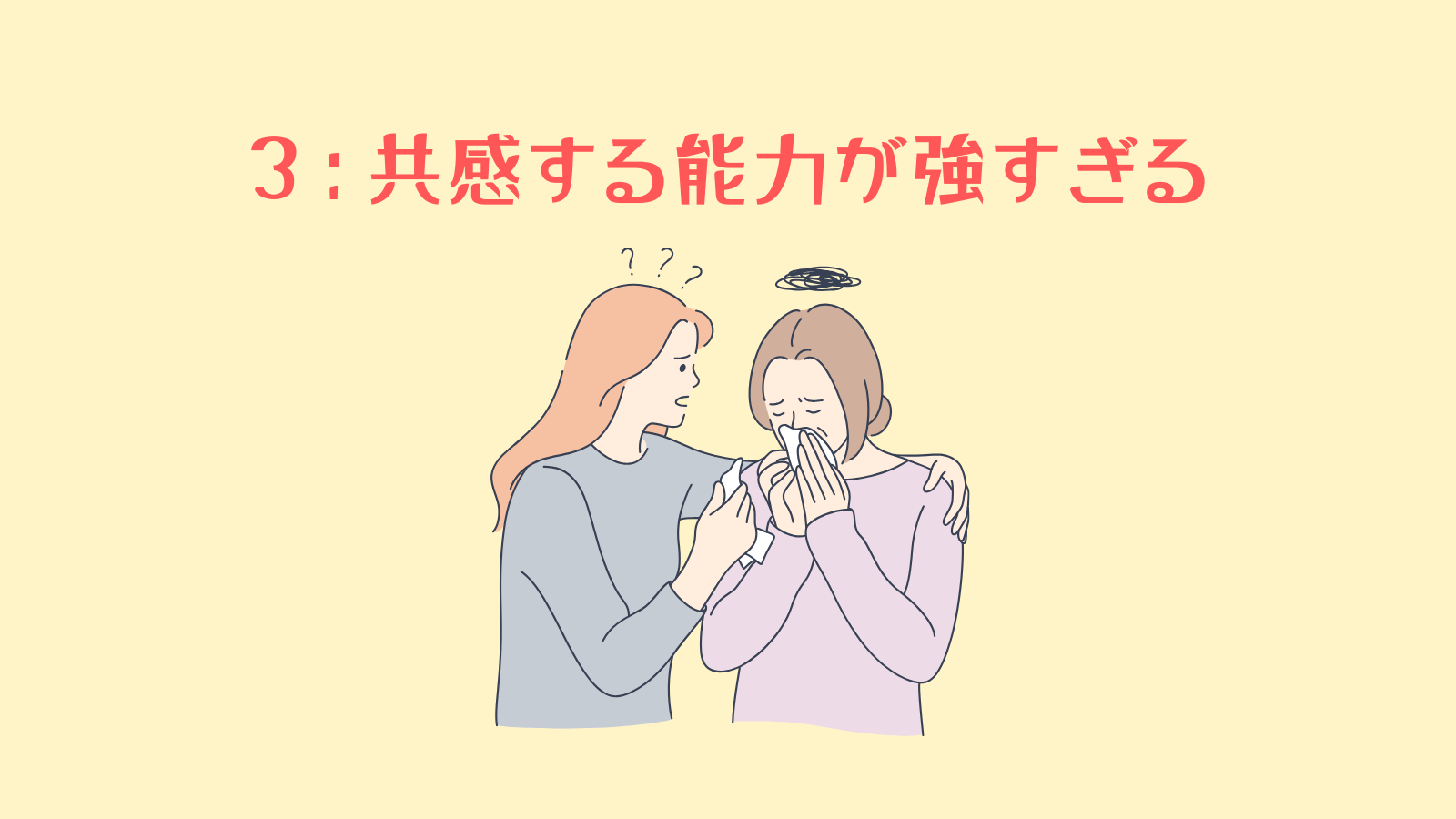
共感力が強すぎる人、特にHSPの人は相手の感情や状況を自分のことのように感じ取りやすく、その分エネルギーを消耗しやすい特徴があります。
人の悲しみや不安に深く寄り添う一方で、自分の心にまで負担を抱え込んでしまうため、精神的な疲労が溜まりやすいと言えます。
また、周囲に気を配りすぎることで自分の感情を抑え込みやすく、知らず知らずのうちにストレスが蓄積するため、心身のバランスを崩し、疲れやすい体質へとつながってしまいます。
4:自己否定が強い

自己否定が強い人は、失敗や小さなミスを必要以上に自分の責任として受け止め、「自分はダメだ」と思い込みやすい傾向があります。
そのため常に心にプレッシャーをかけ続け、精神的なエネルギーを消耗します。
さらに、人からの評価や周囲との比較にも敏感で、安心して休むことが難しくなります。このような自己否定的な思考は自律神経の乱れにもつながり、心身の回復力を低下させて慢性的に疲れやすい体質を強めてしまうのです。
5:常に何かを考えている
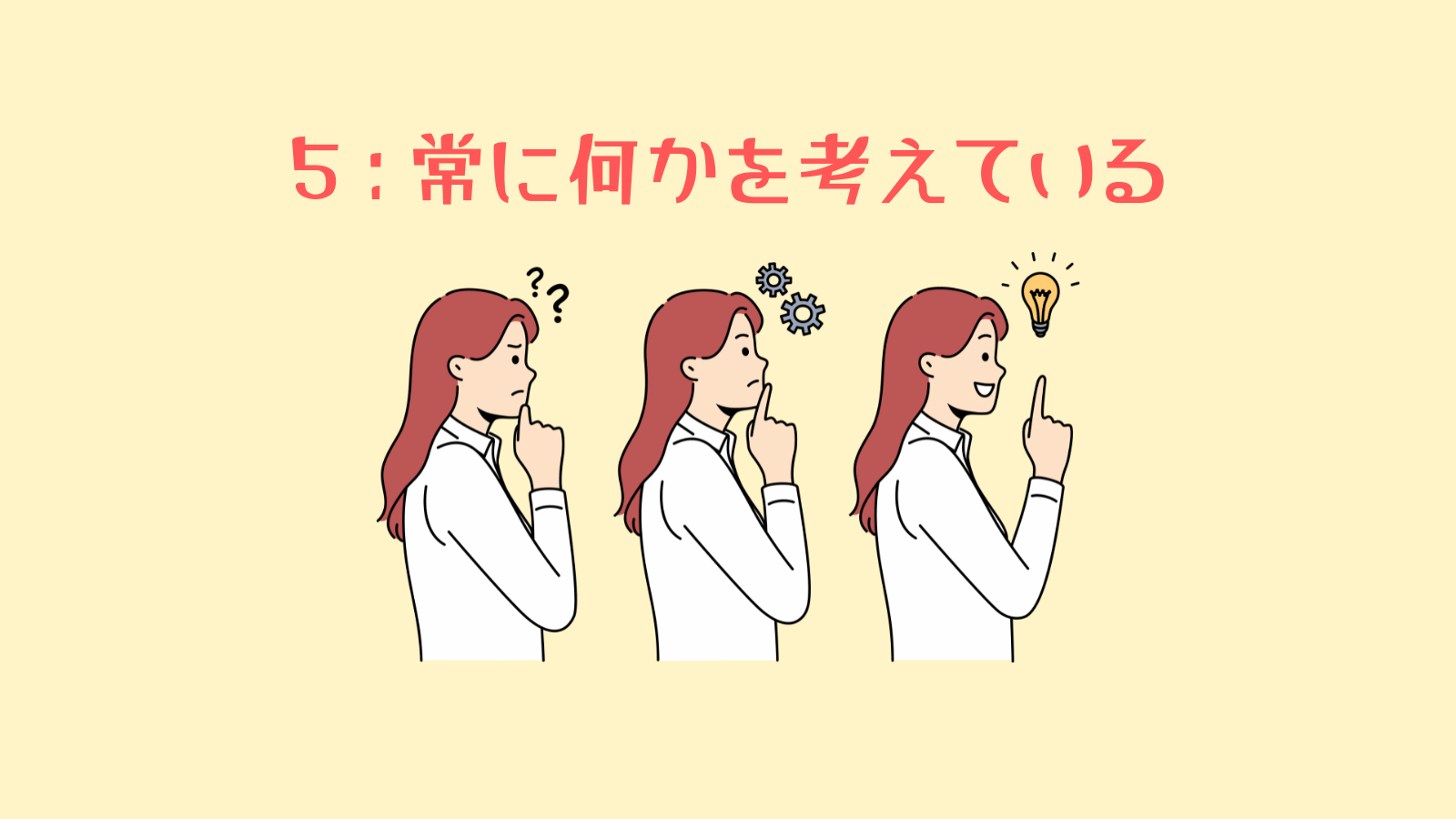
常に何かを考えている人は、頭を休める時間を持てないため、脳がオーバーヒートしやすく疲れやすい特徴があります。
過去の出来事をついつい反省したりまだ来てもいない未来を心配したりと、思考が止まらない状態では脳が常に緊張しており、心身のエネルギーを消耗します。
その結果、集中力や睡眠の質も低下し、休んでも疲れが取れにくくなります。考える力は長所でもありますが、切り替えができないと慢性的な疲労感へとつながってしまうのです。
疲れやすさを改善する原因別の解消方法
疲れやすい体質を改善する方法として、上記の3つがあります。ひとつずつ詳しく解説していきます。
1:生活習慣の乱れによる疲れやすさの場合
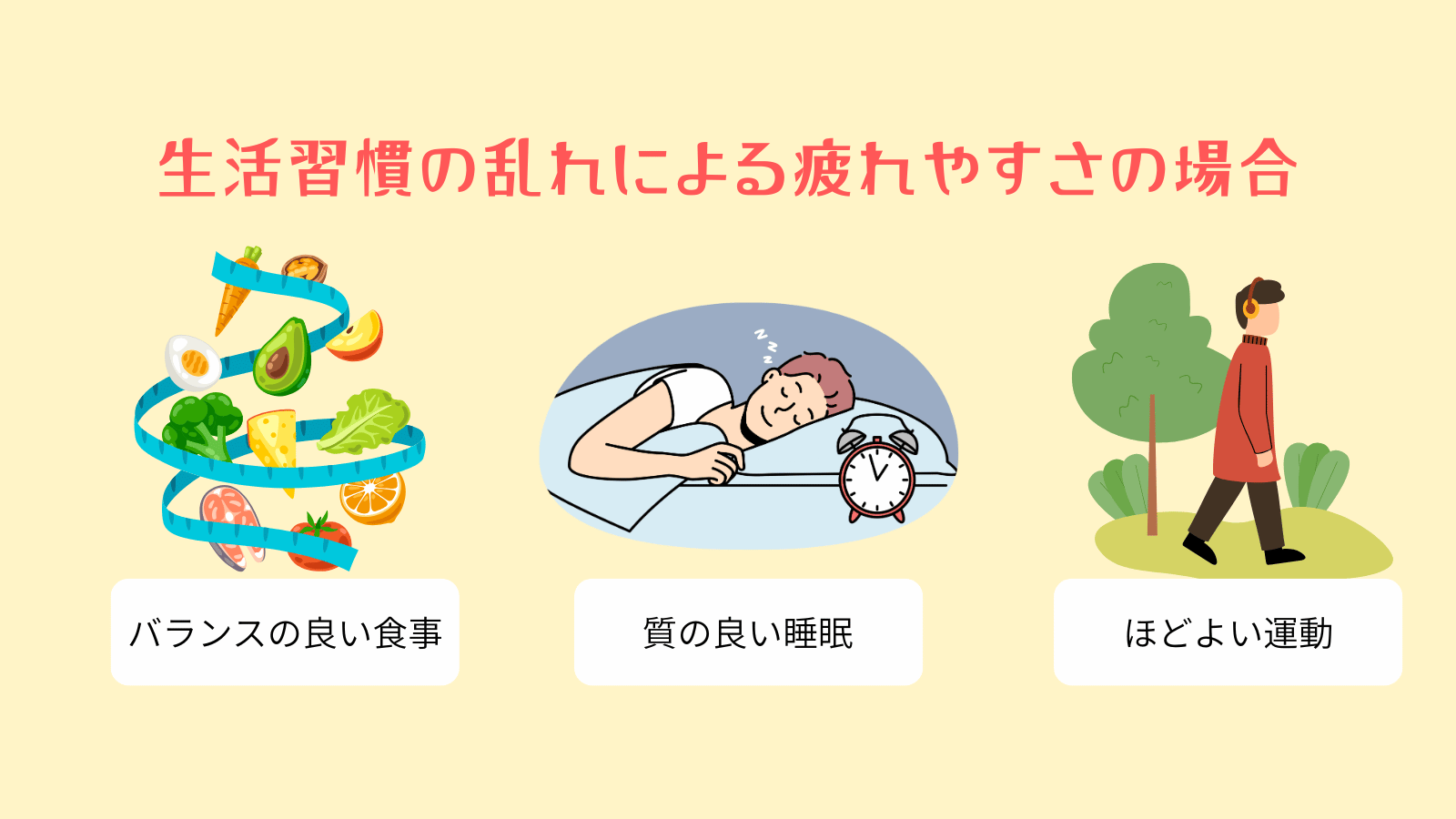
生活習慣の乱れによる疲れやすさを改善するには、まずより良い睡眠を取り、バランスのとれた食事を摂取することや運動を取り入れることが大切です。
毎日ほぼ同じ時間に就寝・起床することで体内時計が安定し、疲労回復力が高まります。食事では栄養バランスを意識し、糖質や脂質に偏らず、たんぱく質やビタミン、ミネラルをしっかり摂ることが必要です。
また、軽い運動やストレッチを習慣にすると血流が良くなり、疲労物質の排出も促されます。さらに、夜はスマホの使用を控えたり、カフェインを夜遅くまで摂らないようにするなど、小さな工夫を積み重ねることで、疲れにくい体質へと整えていけます。
2:環境による疲れやすさの場合
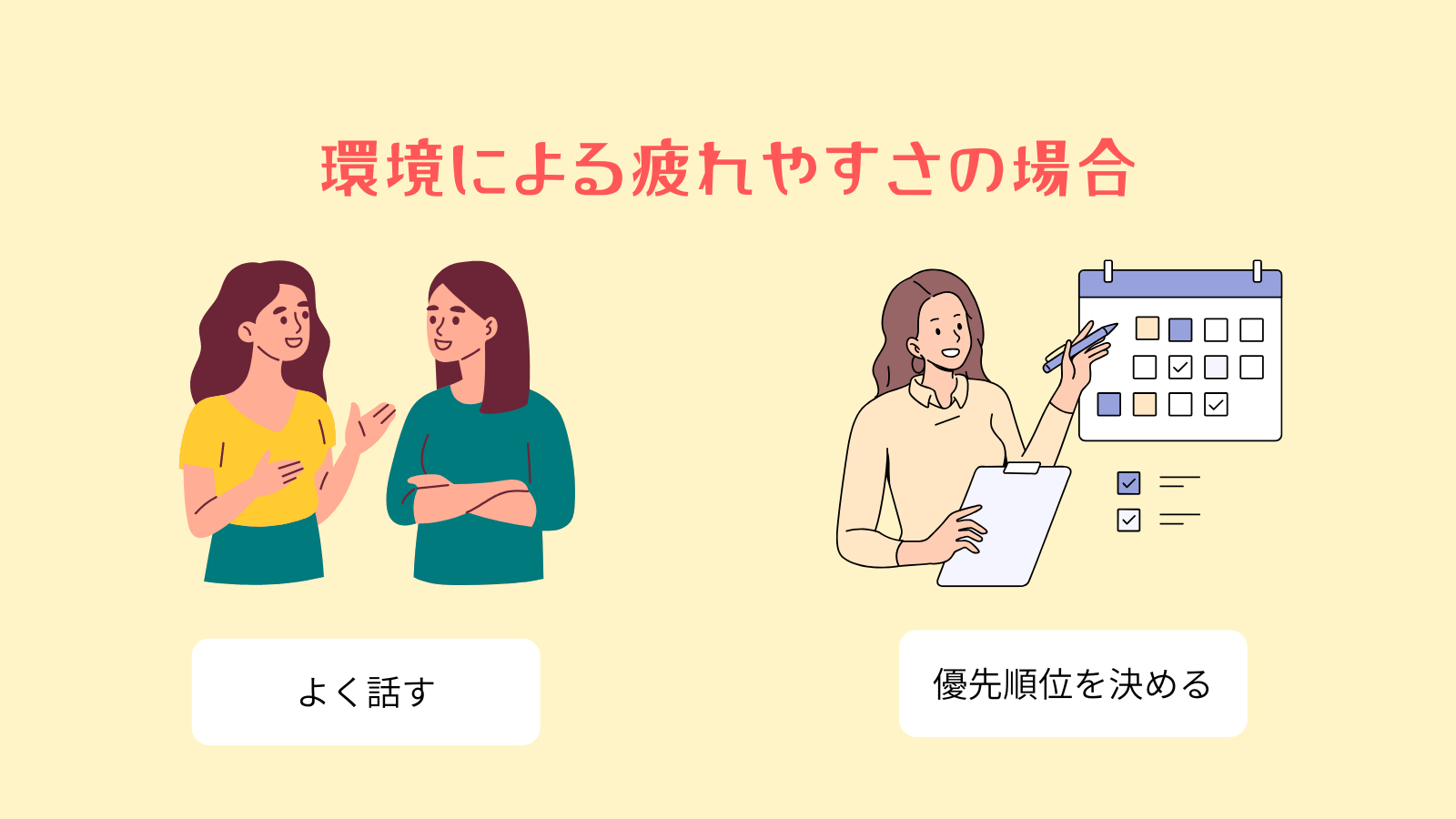
環境による疲れやすさを解消するには、まず自分の心身に負担をかけている要因を見直すことが大切です。
人間関係で疲れを感じやすい場合は、距離をとる・信頼できる人に気持ちを話すなどしてストレスを軽減しましょう。
仕事や家事など忙しさが原因なら、予定に余白をつくり優先順位を見直すことが効果的です。
また、騒音や生活空間の乱れが疲労につながる場合は、静かな環境を確保し、整理整頓を心がけると心が落ち着きます。小さな調整でも「安心できる環境」をつくることが、疲れにくさへとつながります。
3:HSP気質による疲れやすさの場合
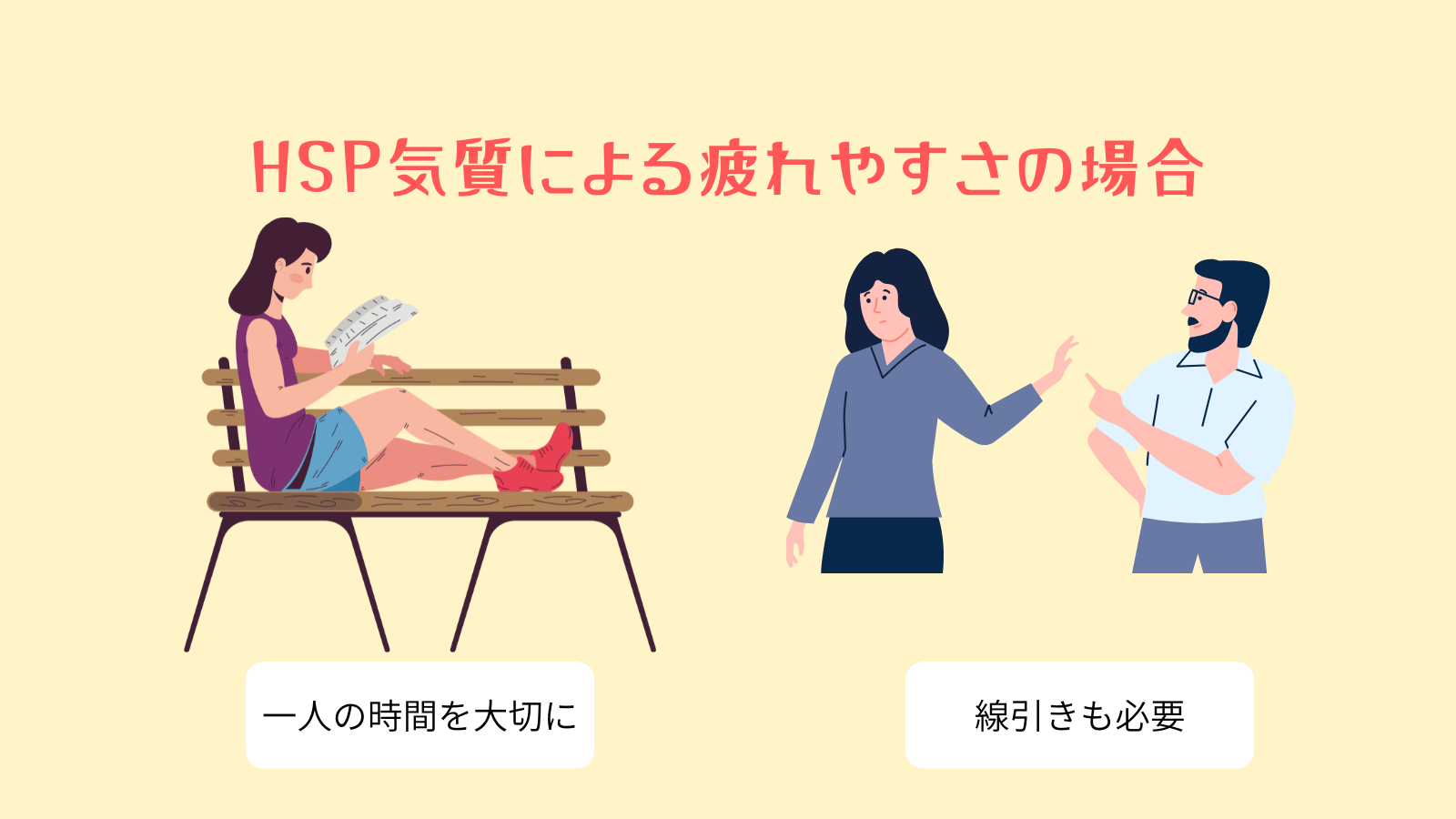
HSP気質による疲れやすさを解消するには、まず「自分は刺激に敏感なタイプである」と理解し、その特性に合った環境を整えることが大切です。
人混みや大きな音など強い刺激から距離をとり、静かな場所や一人になれる時間を意識的に確保しましょう。
また、相手の感情に共感しすぎて疲れる場合は「これは相手の問題」と線引きをすることも有効です。好きな音楽や自然の中で過ごす時間を増やすなど、安心できる習慣を取り入れることで心身をリセットしやすくなり、エネルギーの消耗を防げます。
必要に応じて専門家に相談しよう
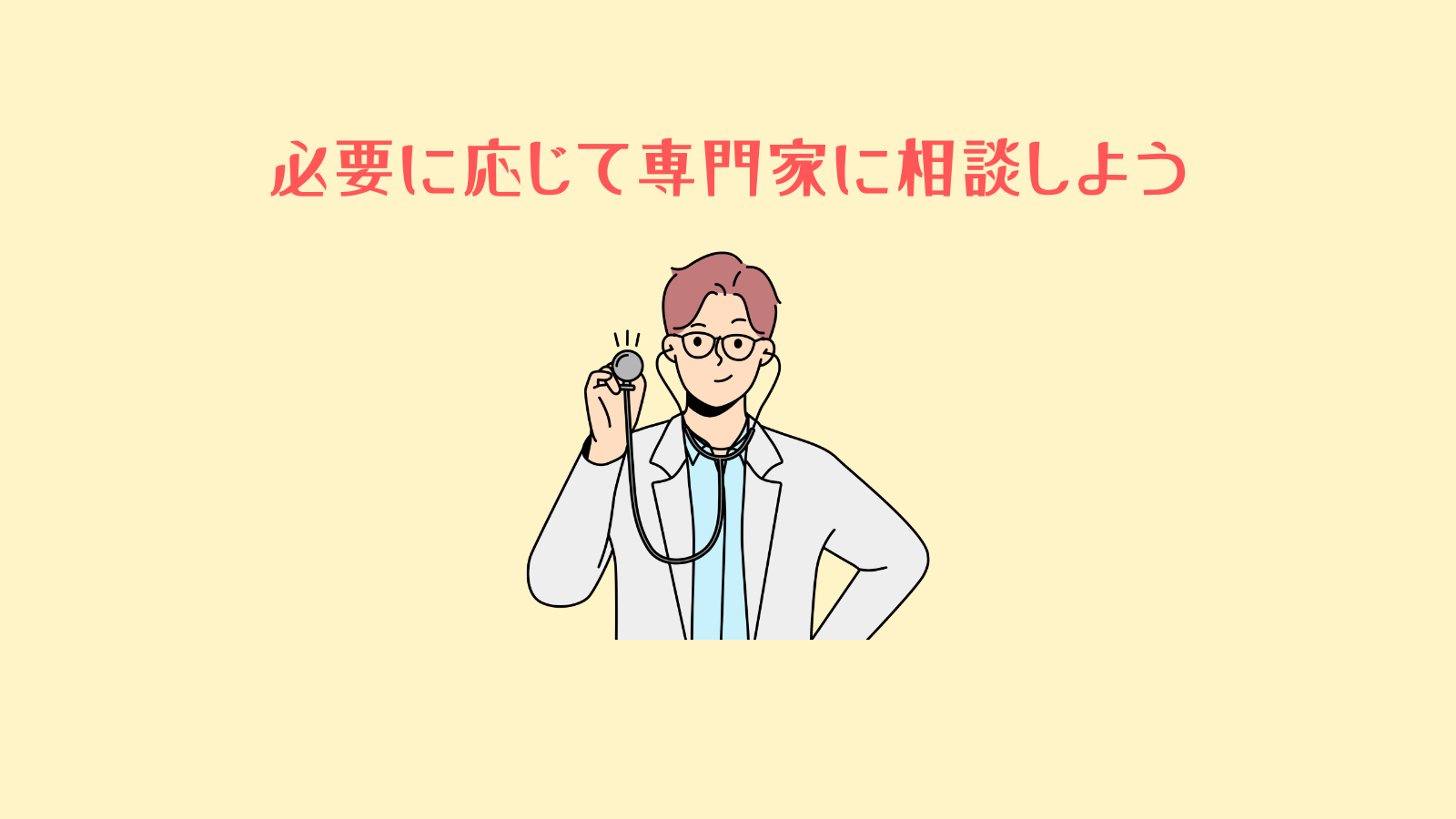
疲れやすさが長く続いたり、日常生活に支障をきたすほど強い場合には、自己対処だけでなく専門家に相談することが大切です。
心療内科や内科では、体の不調や自律神経の乱れ、睡眠障害などを医学的に確認できます。また、心理的な要因が強い場合は、カウンセラーや精神科医に相談することで思考の整理やストレス対処法を学べるでしょう。
自分ひとりで抱え込むと改善が遅れ、疲労が慢性化する恐れがあります。必要に応じて専門家の力を借りることは、自分を守り、より健やかな生活を取り戻すための前向きな選択といえます。
精神科・心療内科のなかには、当日予約をしなくても受診できるところがありますので、気軽に相談してみましょう。
まとめ
・疲れやすい体質の原因は、生活習慣、環境、HSPや虚弱体質などがある
・完璧主義や周囲の目を気にしすぎたり、自己否定が強すぎる人が疲れやすい
・疲れやすさを改善するには、良質な睡眠と適度な運動、バランスの取れた食事を摂るようにしよう
・必要に応じて専門家に相談しよう
疲れやすさには生活習慣の乱れ、環境のストレス、HSP気質など様々な要因があります。改善には、規則正しい睡眠や食事、運動で体を整え、環境を調整して心を休める工夫が大切です。
また、自分の特性を理解し、刺激から距離を取ることも有効です。疲れが長引く場合は専門家に相談し、早めに適切なサポートを受けることが心身の健やかさを保つ近道となります。